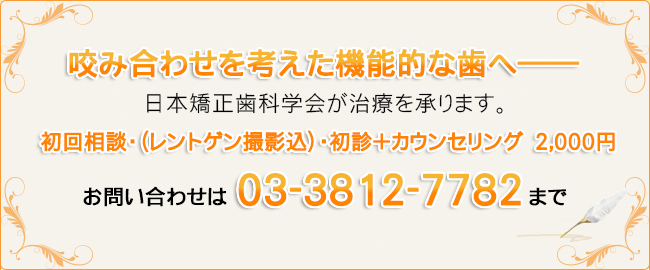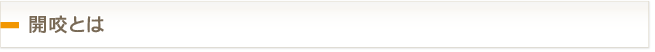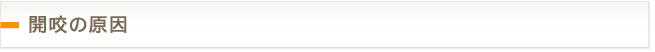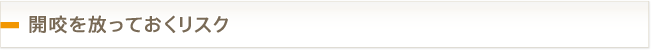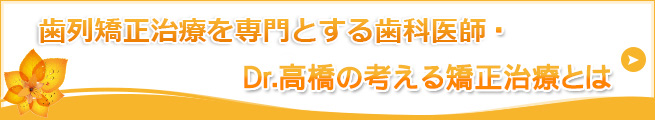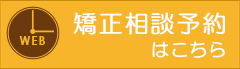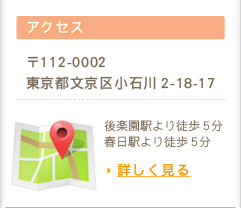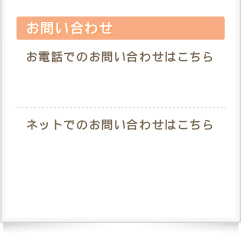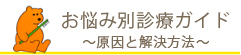なんらかの原因によって正しい咬み合わせができていない状態を、専門的な言葉で「不正咬合」と言います。不正咬合にはいくつかの種類があり、それによって矯正の方法は異なります。こちらでは、文京区の高橋矯正歯科医院が矯正治療を承っている代表的な不正咬合のひとつ「開咬(オープンバイト)」についてご説明します。
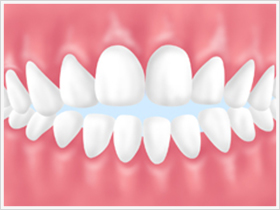
奥歯がきちんと咬み合っている状態にもかかわらず、前歯が咬み合わず口を閉じられない状態を「開咬」と言います。言葉自体にはあまりなじみがないかもしれませんが、決して珍しい症状ではありません。12~20歳においては、10人に1人は開咬、またその傾向があると言われています。
開咬の原因は大きく3つに分かれます。
幼少期の癖 |
小さな子供によくある癖が開咬の原因となることがあります。指を前歯に押し当てるようにしておしゃぶりする癖や、舌を歯で軽く咬む癖、頬杖をつく癖などを継続的に行うことで徐々に歯が動き開咬になってしまうのです。 |
|---|---|
呼吸器系疾患 |
鼻炎や蓄膿症といった呼吸器系疾患がある場合、鼻がつまることで普段から口呼吸をする癖がついてしまいます。口呼吸ばかりしていると、唇や口腔内の筋肉のバランスが崩れ、開咬になってしまうことがあります。 |
遺伝によるもの |
開咬は骨格的な問題から起きることがあります。顎の形が特徴的である場合は、遺伝が原因だとされる症例も少なくありません。 |
| 顎の骨・関節を痛める | 前歯で食べものを咬めないため、奥歯でばかり咬むことになり負担が集中し、顎を痛めてしまいます。 |
|---|---|
| 胃腸障害・嚥下障害を 起こす |
食べものを細かく咬み砕けず、うまく飲み込めなくなる(嚥下障害)だけでなく、胃腸障害を起こすケースもあります。 |
| 発音障害 | 歯並びが悪いことによる発音が悪くなる場合があります。 |
| 虫歯・歯周病になりやすい | 常に口が乾燥している状態になり、細菌が繁殖しやすい状況になります。結果、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまいます。 |
| ウイルス性の病気に かかりやすくなる |
口呼吸がメインになることで、風邪やインフルエンザなど、空気感染するウイルス性の病気にかかりやすくなってしまいます。 |
| 発音障害 | 歯並びが悪いことによる発音障害もあります。 |
開咬には2つの種類あります。ひとつは、下顎が後ろに下がってしまっているパターン。もうひとつは下顎が前にでてしまっているパターンです。通常、開咬の治療は、奥歯(小臼歯)を抜き歯を動かすスペースを作って矯正を行います。ただし、顎の骨が極端にずれている場合は、外科的手術を行う場合もあります。いずれの場合も、高さの調整などをし、見た目だけでなく機能性を意識した治療を行います。